合気道講習会2 合気道技への合気三原則の適用
★たつひとの合気道技法★
合気道の極意を技に展開して
<いつも工事中>

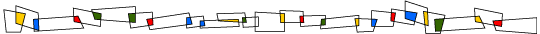
◆ここでは,どのようにして合気の原理を技に適用していくかを考えていこうと思います◆
旧版: 2020/2/17 改訂版へ
誌上 合気道講習会
しじょう あいきどうこうしゅうかい
Website Lectures
| シリーズ | 講習内容 |
| 講習会シリーズ | 「合気道の極意を技に展開して」 『体の常識,合気の非常識。 合気の常識,体の非常識』 Aikido using Aiki of Aikido Do with Aiki of Aikido 合気道講習会 1 「合気動作と三原則」 合気道講習会 2 「合気道技への合気三原則の適用」 合気道講習会 3 「基本の技法に深く蔵されている極意」 (^-^)v |
| 稽古シリーズ | 「合気道の極意を技に展開して」 合気道稽古 1 「三つのポイント」 合気道稽古 2 「合気と合気動作」 (^-^)v |

合気道講習会 2
あいきどうこうしゅうかい
Website Lecture 2
| 講習会2 | 講習内容 |
| もくじ | <合気道講習会 2> 「技への合気三原則の適用」 ・開講/講習会を始めるにあたって ・固め技への適用 ・投げ技への適用 ・四方投げ ・入身投げ ・天地投げ ・閉講/講習会を終わるにあたって (^-^)v |
[▲Top]

第2回講習会を始めるにあたって
| 講習開始 | 講習内容 |
| 初めに | では,第2回合気道講習会として「合気道技への合気三原則の適用」と題し,講習を始めたいと思います。 今日は,弐段を取得するまでに修得した合気道の技,審査技に合気三原則を適用して,柔術である合気道技から合気柔術 あいきじゅうじつ である Advanced Aikido へ進化させることに挑戦してきたいと思います。 これができると,身長185㎝超,体重100㎏超の人を合気道技で投げることができるようになります。凄いですね。 合気柔術にする前の合気道の技では,まだ上腕筋肉に頼って技を行うので,大きな人を相手にすると上腕の筋肉を損傷することがあります。豪州でも,日本から来た参段,四段の人が上腕を痛めて,合気道ができなくなってしまうところを見てきました。 日本から来て日本発祥の合気道で負けるわけにはいかないという気負いが,力感覚の上腕を発動させてしまうのです。注意してください。 それでは始めたいと思います。 まずは,固め技から次いで投げ技を稽古していきます。 全体の技の手順は,理解している人の講習です。また,受けが十分にできないと怪我をしてしまいますので,相手を見ながら十分注意してください。 私が技を行うときには,一つ一つ,受けをする方に確認してから行います。首が鞭打ち症になったり,顔面を床にたたきつけることになってしまいますので。 では,始めましょう。 (^-^)v |
| 写真とビデオ撮影について | <写真とビデオ撮影について> 写真は撮っていただいて構いませんが,ビデオ撮影はご遠慮ください。デジカメやスマホで動画を取るのもビデオと同じことですのでご遠慮ください。 まだまだ研究の段階です。中途半端なものが残ってしまうのは今後の混乱になりますのでご協力ください。 ここでの内容を身体の中に覚えさせていってください。 お約束です。 (^-^)v |
[▲Top]

固め技への合気三原則の適用
かためわざへのあいきさんげんそくのてきよう
Apply the three principles of Aikido to control pinning techniques
| 固め技 | 講習内容 |
イントロ | <固め技への合気三原則の適用> 固め技,特に一教はたくさんの手法があると思います。皆さんの技にどう三原則が生かせるか考えながら,修得してください。 合気道,Advanced Aikido は考えることで習得できます。したがって,ある程度,年齢がたたないと修得が難しいと思っています。合気の動作・操作には,体の感覚が使えないからです。 一教の表では,相手の打ちの捌き方,相手の腕の落とし方,座り極めに合気三原則を適用します。技を行うときに「真中」は必須ですが,特に重要な場面では,再度,指摘していきます。 一教の裏では,裏へめぐりながらの捌きに合気三原則を適用します。 また,面白い,秘伝となっている柔術操作も紹介していきます。 二教は,裏の立極めの仕方です。 三教は,立極めからの落とし方です。 四教は,表の立極めへの合気三原則の適用です。 昔,十分崩してから,極めに入るようにと指導されました。これは弐段までの人に対する指導で,弐段以上の人は,どのような位置からも極めができないといけません。合気柔術操作ではそれが可能です。 また,勢いとか,タイミングとかはほとんど合気動作には無縁です。そのような言葉は,柔術動作で必要なものです。 では,始めましょう。 (^-^)v |
一教 | 第一教 ・技の操作では,いつも自分の前,真中で相手を操作する この合気三原則の「真中」は常に必要です。 <一教表> <一教の表: 打ちに対する操作> ・一教で相手が上段から打ってきます。 この打ちに対する捌き方からです。 色々な捌き方を習ったと思います。 先生によって,それぞれです。 ・ここでは,合気を使った捌きです。 一教運動,これは立派な合気の動き,合気動作です。 内肘が開き,前腕が活動していることがわかります。 ・この一教運動を道場で教えなくなっています。 意味するところは,合気の動きが理解できていないことに尽きると思います。 ・ここではさらに進めて,打ちの方向を合気で,瞬時に変えてしまう方法です。 米谷守正先生の「削ぎ出しそぎだし」です。 ・「削ぎ出し」は,合気上げの操作の進化版です。 ・合気上げは,親指を固定し,小指と薬指で,内肘の角度が開くように 手を上方へ上げていきます。 ・「削ぎ出し」は,親指を固定し,手刀部で,内から外へスライドさせながら, 手を外へ動かすと同時に斜め上方へ移していきます。 錆やペンキをスクレパーで,削ぐイメージから,「削ぎ出し scrape out」の 名称を付けました。命名はTatsu Originalです。 ・相手が打ってくると同時に,相手に正対します。 これは,合気三原則の真中です。 右手,左手を上下に位置させ,腰を相手に向け,体を正対させます。 これで自己の100%の力がだせることになります。 次いで,削ぎ出しです。 ・この削ぎ出しは,右手の甲の方から相手の外肘に。 相手の外肘が手の甲に触れる瞬間に実施します。 ・静止状態からも有効です。 相手の外肘に甲を当てた状態からスタートします。 ・左手はまだ相手の腕に接触していなくて大丈夫です。 ただし,左手も前面真中位置させることが, 体を相手に正対,真中に置くことになります。 ・相手の背が高く相手の肘に手が届かないときは,上腕の外側に対して実施します。 ・一教の打ちに対しては,「相手の手首をもって」という指導は, 身長が比較的同じ日本人の弐段までの基本技の指導法と理解してください。 ・この削ぎ出しにより,相手の打ちが方向が変わり,次の腕落としの段階になります。 <一教の表: 腕落としの操作> ・弐段までの審査技では,相手の上腕を掴んでと今まで教わったと思います。 ・合気動作では,相手の上腕に,自己の体重を乗せて行きます。 上腕に,60kgを載せられたら,体を保持できる人はいません。 ・これは重力落としです。 効率的に,連続して行うため,私の場合は,左手の手刀部を使い, 大根の回し切りの要領で,自己の体重を相手の上腕に乗せていきます。 必要なら前腕の手刀部(尺骨部)も使います。 手刀部の広義は,手の手刀部と腕の尺骨部を合わせていいます。 これを,合気下げという言い方もあります。 ・受けは腕を回し落とされる感覚です。 力がかかる部位が移動し,かつ60kgの重さで行われるので対応のしようがありません。 ・右手は軽く相手の手首をもっています。 ・この腕落としは,床に到達するまで行います。 途中,受け自体の自重による自然落下も腕落としの操作に 加勢してくれます。 ・ここが,審査技とは違います。 審査技では床まで落とすことができません。 ・相手 (受け) は,持たれていない方の手を床につき,体の落下を調整しないと 顔面を床に叩き付けてしまいます。 ・腕落としで,どちらの足から出すかとかは関係ないことがわかると思います。 相手が比較的,立った状態でも可能です。 <審査技の一教の腕落とし> ・審査では,腕落としは膝の高さまで,その後は, ・相手の腕の三脚机の引き落とし ・相手の腕の頭方向への押し回し落とし ですね。右と左で分けてやるのもいいですね。 審査で,膝の高さから二の腕への伸張力を使った重力落としもいいです。 伸張力を維持したまま「ただ座るだけ」です。 「三脚机の引き落とし」と「上腕重力落とし」を組み合わせると 場所もとらず良いかもしれません。 <一教表: 座り極め> ・座り極めの,相手(受け)の上腕への極めです。 腕落としと同じく,大根の回し切りで,自己の体重を 相手の上腕に載せていきます。 <面白い一教の柔術操作> ・座り極めにおいて,相手に近い膝頭を相手の脇腹に接触させます。 これ「痛い」です。 相手が極めの時,身体を動かさなくする方法です。 他方の膝を相手の手首にあてることで,両膝だけで相手を動けなくできます。 これは,守央道主の本に記載されていますが, 行っている道場はほとんどみません。 ・相手が床に落としたあとも,ダンゴ虫や潰れたカエルのようになっている場合。 相手の背中の中央の背骨の上に,近い方の肘を乗せ, ゴリゴリ圧迫します。静的当身ですね。 これ「痛い」です。背骨を傷める可能性があるので手加減が必要です。 ・極めが終わり,相手から離れるときに, 腕の位置はそのままに,手掌のみ抑えたまま,体を開き,離れる動作です。 相手は動けません。 腕を相手の両肩の線から,10~20度上で,手掌を上に向け, 腕が伸びた状態で,軽く自分の手掌や,指一本でも抑えればできます。 この操作は,本当の意味での「pining」です。 相手の中指を引っ張ってもできます。 手掌に拳をのせてもよいです。 相手の手掌に膝を載せると,両手が自由につかえることになります。 いずれの場合も,相手受け自身の体が邪魔になって起き上がることができません。 デモとして,恰好がよいです。 以上が,一教に対する柔術技の秘伝に属するものと思います。 <一教裏> <一教の裏: 打ちに対する操作> ・相手の打ちに対しては,表と同じですが, 体がすでに,相手の裏側面に移動しているので, 相手の打ちの方法はほどんど変わりません。 <一教の裏: 腕落とし> ・裏ですから,廻りめぐりです。 審査技でも,引っ張っている人をよく見かけます。 ・合気動作では,自己の前面,真中で,相手の上腕を下方へ落とします。 手掌を相手の上腕に載せ,落としていきますが, 体は,相手の後ろ側面に踏み込んだ左足を中心に,背転します。 したがって,見ている人からは,螺旋らせん状に落ちていくように見えます。 ・相手は,上腕の上に60kgまで載せられ,回されるので, 受けをとるしかありません (^-^)v |
| 二教 | 第二教 <二教裏: 立極め> ・二教の立極めは,すでに弐段なら手の形,腕の形,肩への当て方等 テクニックを色々お持ちと思います。 ・合気動作のポイントは,一つ。 自己の動きを,相手の中心,丹田に腕を通じて連結させることです。 ・相手の真中と自己の真中の連結です。 ・練習は,交差取り(相半身片手取り),逆半身片手取りでの 片手二教立極めです。最後は諸手取りでの稽古です。 これができれば,相手の真中を連結させたことになります。 ・弐段以上の人ですから受けは大丈夫と思いますが, 腕から出るボキという音,口からでる「ギャ」はまずいと思います。 では,始めましょう。 (^-^)v |
| 三教 | 第三教 <三教裏: 立極め> ・合気動作の適用は, 三教の場合も,裏の立極めです。ただし,立極めそのものではなく, 立極めからの崩しです。 <三教裏: 立極めからの落とし> ・審査技では,釣り竿を投げるように前方に相手の腕を放り投げるか, 三教を極めながら,よりひねり回し落として,途中から, 空いている方の手を相手の上腕に押し当て落とします。 ・釣り竿投げは,前腕伸張力を使った合気を使っています。 相手が100kgもあるとなかなか投げづらいと思います。 ・合気三原則の重力を使えば,どんな人でも落とすことができます。 相手を三教立極めで,その形で,自分の右胸の位置に固定します。 あとは,ただ座ります。相手も座るのに合わせて落ちてきます。 床まで落としたら,自分の上腕の外側で相手の上腕を クィと押してあげます。 ・相手 (受け) は,空いている方の手で受けを取らないと, 顔面制動となってしまいます。 では,始めましょう。 (^-^)v |
| 四教 | 第四教 <四教表: 表極め> ・審査技の四教の表の極め,きちっとできますか。 崩してから,四教極めにと教わりましたね。 ・腕の太さが生半可でないオーストラリアの人に,効かせられますか。 ・腕は,床に崩してからだと,立っている時よりも太くなっていて, 前腕の筋肉も張っています。 ・では,合気三原則で四教極めを行いましょう。 <四教表: 基本の柔術動作表極め> ・四教は,「手首抑え」で,手首のツボを責めます。 ここで紹介しいる表極めの位置が異なっています。 どちらかというと「小手抑え」ですね。 <四教表: 表立ち極め> ・普段は,三原則は自分に対してですが, 四教の表極めは,相手の体重を使います。 ・相手の前腕を肩より上に位置させ, 自分の人差指の付け根のボールを相手の前腕の中央に当てます。 このボールを丹田で支えて,相手の体重がこのボールの上にのるように します。 ・人差指のボールは,相手の体重がかかるにしたがって, ツボに移動していきます。 相手は,相手の体重が,一つのボールの上にのるツボで受け止めるので これはたまりません。 「ゥワー」ぐらいの声は相手からでます。 ・このボールでツボを前面下方へ,伸張力で押していきます。 容易に,床まで落とすことができます。 ・四教の裏は,柔術系での極めで十分落ちていきます。 では,始めましょう。 (^-^)v |
[▲Top]

投げ技への合気三原則の適用
なげわざへのあいきさんげんそくのてきよう
Apply the three principles of Aikido to throwing techniques
| 投げ技 | 講習内容 |
| 四方投げ | 四方投げ <四方投げへの合気三原則の適用> 四方投げですから,皆さん,お得意と思います。 投げ方も,種々修得されていると思います。 でも,100kg超の人や,肘を体につけ,投げられないように意地悪する人には どうしたらよいでしょうか。合気を使えば,確実に相手を落とせます。 ・四方投げで,相手の手を相手 (受け) の肩に当てて,そのまま座りましょう。 ただこれだけです。三原則の重力の利用です。 ・相手は,四教の形に極められたその手に,60kgの重りを掴ませられたら, たまりませんね。 ・50年前,藤平光一先生は,真下に落とすといっていましたので, 合気の動作のことを言っていたのではと思っています。 では,始めましょう。 (^-^)v |
| 入身投げ | 入身投げ <正面打ち入身投げへの合気三原則の適用> ★★★★ 正面打ち入身投げへの合気動作の適用を稽古したいと思います。 通常は,相手が正面打ちを打ってくるところから始めますが, ここでは,「投げ」から,「起し」,「崩し」,「打ち捌き」の 逆の順番で,投げから打ち捌きへ遡って稽古します。 ひとつひとつの操作に,合気動作を導入することで, 技が数段レベルアップすることが実感できると思います。 レベルアップした技が,合気柔術,Advanced Aikido,の入身投げです。 どの操作ひとつとっても,それだけで投げや押さえができてしまいます。 合気柔術の入身投げは,すべてが合気動作です。 だから入身投げのことを呼吸投げと呼ぶこともあるのです。 たのしみですね。 それではまず,いつも行っている正面打ち入身投げを,二人一組で行ってください。 審査で行う入身投げで,足を一歩踏み出して投げる表投げをしてください。 <投げ> ★★★ 投げる直前の状態で止まってみてください。 そこから,どのように通常投げているか考えてください。 投げた時の想像してみてください。 ・相手が大きかったらどうですか, 一生懸命押していませんか。 ・体が先行していませんか。 体が開いた状態といった方がしっくりくるかもしれません。 ・投げたあと受けを見ていますか,あさっての方向を向いていませんか。 体の向き: 真中 通常の投げが確認できたら,まずは, 体の向きです。合気三原則の「真中」です。 常に,相手を自分の前において投げてみてください。 投げて,床に受けをとる相手を見続けていたら, 真中で投げていることになります。では,二人でここを稽古してください。 ・投げの時は常に相手を自分の「真中」に。 【合気三原則】 手の形 次に移ります。確認です。 合気道の教科書にもでていますが,投げの時, 親指が下になっていますか。 肩の可動範囲が狭くなり,投げの伸張力を効率よく相手に伝達できるようになります。 これは,柔術のテクニックですが大切です。 ・親指先下で 【柔術極意】 伸張力による投げ 投げの一番難しいポイントです。 投げで,押してしまう人がかなりいます。 そこで, ・第三者に,指先に手掌を当ててもらいます。 ・投げる受けのことは忘れて, 指先をあたっている人の手掌を,床に向けて突き押します。 これにより,自分には投げる意識がまったくないにもかかわらず 前腕伸張力で,相手の体に 自己の質量パワーがのり,強烈な投げとなります。 投げた本人は投げた意識がないので, ここが修得を難しくしているところです。 まさしく極意技です。 イメージとしては,指先か柔らかな豆腐に指を突っ込むように操作します。 豆腐でなくて,プリンでもよいです。 これが,前腕伸張力発動の仕掛けです。 <注意> 相手に怪我をさせないために,操作のスピードのコントロールが必要です。 腰投げと同じように投げの感覚がないので, 指を突き出すスピードをコントロールすることが, 投げの強さのコントロールになると認識してください。 以上の操作は,入身投げの起こしの後,いったん止まった静止状態から 行ってできる操作です。合気動作は勢いはいりません。 投げは,真中を維持し,前腕伸張力で相手を投げる。 【合気三原則】 米谷先生の動きです。 <起こし> ★★★★ 【T】 「起こし」は「崩し」によって,前かがみになった相手を起し,反り返らす操作です。 柔術的操作では,相手を肩に当て,体の捻りで相手を起こすことを ならってきたのではないでしょうか。 ・相手が100kg超の巨体が,体重をすべて二の腕や肩越しに掛けた来たら 起すことができますか。 大丈夫です。合気上げで上げます。 合気上げで,天井に向かって,相手を意識せず 指先から差し上げればいいのですが, 頑張ろうと思う気持ちがはたらき 無意識に二の腕が働いてしまい, これがなかなか難しい人は, 投げと同じように第三者に,指先にその人の手掌を当ててもらいます。 その手掌を押し上げください。 簡単に上げることができます。 練習してみましょう。 相手に上腕部に,顔を載せ体重をかけた状態で, 合気上げで相手を起こしてみてください。 従来,自分が行ってきた方法と比べてみてください。 合気上げができれば, 力感覚なしに相手を起こすことができたことになります。 自分の手が,自分の頭より上に上がっていれば, 合気上げによる起こしができています。 あまり,勢いよく上げると これだけで,相手を投げてしまうことになります。 起こしだけによる投げで, 米谷先生のその場入身投げに通じます。 <注意> 合気上げも力感覚がないので, すぅーと上げてしまうと上げがってしまいますが 相手が体を固めていると上腕部分の道着の表面で相手の顔を 擦りあげることになり,相手の唇やほほの一部が やすりで擦ったようなダメージをうけることになります。 相手の顔に擦り傷のような怪我をさせないためにも, 操作のスピードのコントロールが必要です。 指を突き上げるスピードをコントロールすることが, 合気上げのコントロールになると認識してください。 合気上げで相手を起こす 【合気三原則】 気づいている人は150万人の内何人でしょうか (^-^) <崩し> ★★★ 相手の打ち腕の二の腕から内肘にかけて, 伸張力を使い,手刀で重力掛け崩しをします。 相手が床まで崩れていきます。 相手を真中におき,体を垂直にすることが大切です。 相手の腕の上で,片手腕立てを行うイメージでおこなってください。 崩しすぎるとそれだけで技は終わってしまいます。 <打ち腕捌き> 正面打ちに対し,前足から受け側面裏に入りつつ, 相手が打ちにくる打ち腕の外側を擦り上げるように,一教運動で上げていきます。 一教運動は,自分の質量パワーを合気上げで相手の打ち腕に伝達する すごい操作であることはあまり理解されていません。 合気三原則から一教運動を考えると面白いです。 一教運動もどきとの違いも分かってきます。 相手の打ち腕を,攻撃の線から軽い「削ぎ出し」で外すことも有効です。 その後,相手の側面に一歩踏み出し,次の崩しを行います。 投げから,起こし,崩し,打ち捌きと,正面打ち入身投げの合気動作を 三原則を使いながら稽古してきました。 皆さんの技のレベルは, 今日の稽古で二・三倍に上がったのではないでしょうか。 今日は,入身投げの表投げだけです。 入身投げは,起こし操作と投げが一体となったその場で投げ, 受けがその場に背中から落ちる 地獄の入身投げと言われた 米谷守正先生の入身投げまでまだまだ多くあります。 合気三原則を使って,自分の技を考えながらブラッシュアップしていってください。 「今までの合気道はなんだったんだ」と思う必要はありません。 今までの合気道があって,ベースとなる技を 習得してきたから合気技ができるのです。 合気道をしていない人には合気技はできません。 重力掛けで崩す 【合気三原則】 遠藤征四郎先生の崩しです (^-^)v (20191211) |
天地投げ | 天地投げ 天地投げは逆半身両手取りでスタートです。 <天地投げ表> <天地分け> ・天の手は,持っている相手 (受け) の手首を内から手刀で, 切り上げる合気上げです。 ・合気上げで切り上げた時点で,すでに親指が下の状態になって 投げの準備ができています。 <投げ> ・入身投げの投げと同じです。 ・天の手の指先から,受けの肩越しをなでるように, 床に向かって,手を進めます。 指で突き刺すイメージです。 ・投げる感覚がないので,注意しないと, 相手の受けは背中から落ちて, 背中を打って息ができない 状態になってしまいます。 ゆっくり慎重にやってください。 ・素早くこの動作をやると,受けが頭から落ちて 救急車を呼ぶことになります。 最大限の注意を払ってください。 好きな合気道で怪我をする,させるのは絶対に 避けましょうね。 これは合気動作を使った極意中の極意動作です。 内緒ですよ。 ・勢いは全くいりません。 静止状態から行ってください。 合気に勢いはいりません。 勢いがいるのは柔術です。 <天地投げ裏> <天地分け> ・相手の側面裏に前足から,歩を進めます。 裏に進めた方の手が地の手になります。 ・反対の手が天の手になります。 天の手は,手刀で切り上げながら, 甲が自分の顔の前にくるようにします。 「手鏡」という口伝があります。 自分の甲に付けた手鏡ですから, 自分の顔が見えないといけません。 顔が見えるということは,真中です。 ・一方,地の手は,手掌を上にして,体の前,真中に位置させます。 <廻り> ・天の手は自己の顔の前,すなわち真中をそのままに, 手掌上に向けた地の手を指先から,中段を維持し 自己の中心,真中へに向かって突き進めます。 同時に裏へ転換します。 転換は,軸足を中心に何度でも何回転でも めぐることができます。 <投げ> ・投げは表と同じです。 ・裏巡りときの手掌が上の地の手を,手掌を地に返し, あとは,天地投げの表と同じ,一歩踏み出して,指先先行で 伸張力を使って投げます。 (^-^)v (20191215) |
[▲Top]

講習会を終わるにあたって
では,「合気道の極意を技に展開して」と題する講習のシリーズの第二回として行った「合気道技への合気三原則の適用」についての講習を終えたいと思います。 本日の講習のテキストや市販されている本はありませんが,技法としての合気については,武田惣角先生の直弟子の佐川幸義先生に関する「孤塁の名人」「透明な力」が参考になります。これら本にでてくる動きをすべて体現するように考えてみてください。ともに文庫本で購入できましたが現在では絶版になってしまいました。「孤塁の名人」の方は,電子書籍で購入可能です。 合気の動きについては,岡本正剛先生のビデオや菅沼守人先生の講習会の様子がyoutubeで見ることができます。探してみてください。 合気は自分で考えない限り自分のものになりません。自分に対する「マインドコントロール」を上手くつかって獲得してください。頑張ってください。 参加,ありがとうございました。 (^-^)v |

[▲Top]

本ホームページの作成者・管理者: 高橋達人 たかはしたつひと tatsuaiki7@gmail.com
