合気道講習会3 基本の技法に深く蔵されている極意
★たつひとの合気道技法★
合気道の極意を技に展開して
<いつも工事中>

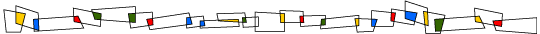
◆ここでは,合気道の基本の技法中にある極意を見ていきたいと思います◆
旧版: 2020/2/17 改訂版へ
誌上 合気道講習会
しじょう あいきどうこうしゅうかい
Website Lectures
| シリーズ | 講習内容 |
| 講習会シリーズ | 「合気道の極意を技に展開して」 『体の常識,合気の非常識。 合気の常識,体の非常識』 Aikido using Aiki of Aikido Do with Aiki of Aikido 合気道講習会 1 「合気動作と三原則」 合気道講習会 2 「合気道技への合気三原則の適用」 合気道講習会 3 「基本の技法に深く蔵されている極意」 (^-^)v |
| 稽古シリーズ | 「合気道の極意を技に展開して」 合気道稽古 1 「三つのポイント」 合気道稽古 2 「合気と合気動作」 (^-^)v |

合気道講習会 3
あいきどうこうしゅうかい
Website Lecture 3
| 講習会3 | 講習内容 |
| もくじ | <合気道講習会 3> 「基本の技法に深く蔵されている極意」 ・開講/講習会を始めるにあたって ・準備運動 ・一教運動と船漕ぎ運動 ・転換 ・諸手取り呼吸法 ・固め技の中の極意 ・一教 ・投げ技の中の極意 ・入身投げ ・閉講/講習会を終わるにあたって (^-^)v |
[▲Top]

| 講習開始 | 講習内容 |
| 初めに | では,第3回合気道講習会として「基本の技法に深く蔵されている極意」と題し,講習を始めたいと思います。 開祖の言葉の中に, 「極意は日常の教えの中にあり,基本の技法の中にこそ深く蔵うせられている」 というものがあります。 今回の講習会では,日々道場で行っている普段の稽古の中で行う体操,転換法,諸手取り呼吸法,正面打ち一教,小手返し,入身投げ,四方投げ,天地投げ,そして最後に座技呼吸法 この基本の技法の中に,どこに「極意」,すなわち「合気」が,蔵されている,しまい込まれているのかを日々の稽古の順番をたどりながら考えていきたいと思います。 技の「極意」は,三つのポイント,合気三原則「真中」「重力」「前腕伸張力」でどうしまい込まれているかを見ていきたいと思います。 では,始めましょう。 (^-^)v |
| 写真とビデオ撮影について | <写真とビデオ撮影について> 写真は撮っていただいて構いませんが,ビデオ撮影はご遠慮ください。 デジカメやスマホで動画を取るのもビデオと同じことですのでご遠慮ください。 まだまだ研究の段階です。中途半端なものが残ってしまうのは今後の混乱になりますのでご協力ください。 ここでの内容を身体の中に覚えさせていってください。 お約束です。 (^-^)v |
[▲Top]

合気体操・転換の中の極意
あいきたいそう・てんかんのなかのごくい
| 体操 | 講習内容 |
| 準備体操 | <準備体操> まずは,体操からです。各道場,先生によって順番は異なりますが,部分ごとの体操はあまりかわることはありません。 <手首振動運動> ・両腕を頭上に上げ,手首を振る手首振動運動は,上腕の三頭筋と前腕を使います。 いずれも,力感覚を持たない筋肉を使った運動です。 ・この運動をするときは,力強さを感じない前腕伸張力が実際発動している状態を 作っているのです。 ・同様に,両腕を下ろしての手首振動運動も手首を振り動かすことで, 前腕伸張力を使います。 気が付かないけれど,きちっと合気動作に必要な三つのポイントの内の 一つである「前腕」の準備運動を行っているのです。 (^-^)v |
| 一教運動 | <一教運動> ・一教運動も,これを行うのは,一教がうまくなるためと思って行っていた人も多いと思います。 ・一教運動の重要さ,凄さを認識していない道場では,一教運動が次第に 準備運動に取り入れられなくなっていっていると思います。 <一教運動の基本的動き> ・まずは,右半身からスタートします。 ・両手を軽く握り,両腰の脇に持ってきます。 甲を外に向け,拳の指の背を腰に付けます。 ・両手を手刀状にしながら,前方上方に向かって,手刀先行で上げます。 手を上げるにしたがって両足均等荷重から前足荷重になります。 ・足は半身を保ち位置を変えずに行っても, 前足から前進する送り足で行ってもよいです。 ただしどちらの場合も,体はほぼ垂直に, 後足の踵はあげずに,床についた状態で行います。 ・手を挙げ終わったら,腰を引きつつ,両手を腰の位置まで戻します。 戻す時に,腰をやや引き気味にしますので,後足荷重となります。 ・これを数回づつ,左右行います。 <どこに極意が> ・右半身から両手を軽く握り,両腰の脇に持ってきます。 ・内腕が閉じました。「伸張力」が発揮できる準備です。 ・この時,すでに腰は前方に向かって正対しています。 すなわち,前方が「真中」になっています。 ・両手を手刀状にしながら,前方上方に向かって,手刀先行で上げます。 ・左右の手は前方に向かって平行に並んでいます。 すなわち,腰から上は,手に至るまで「真中」を維持しています。 ・指先先行で上げていきますが,さらにポイントは,小指,薬指先行です。 これにより,前腕伸張力が発動 (activate) します。 動的伸張力です。 内肘の角度が開いていくことで,きちっとできているかの確認ができます。 ・この両手の動きは,「合気上げ」そのものです。 ・手を上げるにしたがって両足均等荷重から前足荷重になります。 ・体の前方への移動です。質量パワー,「体の合気」の発動です。 ・60kgの質量パワーです。「重力」ですね。 ・このパワーが,動的伸張力を通じて指先に伝達されます。 一教運動は,合気三原則「真中」「前腕伸張力」「重力」の三つのポイントすべて 含んだ準備運動となっています。 ここで,十分でない部分を矯正することができます。 また,極意とは何かを考えることもできます。 (^-^)v |
| 船漕ぎ運動 | <舟漕ぎ運動> ・「船漕ぎ運動」は,神道で行われる「天の鳥船の行 あまのとりふねのぎょう」とも言われている ようですが,方法は微妙に違うようです。 ・ここでは,私が大学時代に教わった「船漕ぎ運動」をベースに, どこに極意があるのかを見ていきたいと思います。 <舟漕ぎ運動の基本的動き> ・まずは,左半身からスタートします。 ・両手を軽く握り,両腰の脇に持ってきます。 甲を前方に向け,腰に付けます。 ・甲から,前方下方向かって,甲を先行で突き出していきます。 甲を突き出すにしたがって両足均等荷重から前足荷重になります。 足は半身のままの状態で行います。 ただし,体はほぼ垂直にして行います。 ・スタートは,船漕ぎですから手を前に伸ばしたところからの 方が正のようです。声掛けは,引いたときに「エィ」, 突き出したときに「ホゥ」です。 混乱している人もまま見られます。 <どこに極意が> ・右半身から両手を軽く握り,両腰の脇に持ってきます。 ・内腕が閉じました。「伸張力」が発揮できる準備です。 ・この時,すでに腰は前方に向かって正対しています。 すなわち,前方が「真中」になっています。 ・前後の体と腰の動きが,前後方向の「体の合気」です。 (^-^)v |
| 転換法 | <転換法> ・転換法も,合気道をはじめたころは,この動作を何のためにするのか 分からずに行っていた人も多くいると思います。 ・転換法も多くのやり方があります。 ・どのような体格の人にも通用する、自分に合った方法を身につけてください。 ・一番のポイントは,真中です。 (^-^)v |
諸手取り呼吸法 | <諸手取り呼吸法> ・諸手取り呼吸法ですが,本来諸手取りですが,ポイントが分かりやすい逆半身片手取りで行いたいと思います。 ・手を頭の上まで上げれば,いわゆる呼吸力が使えたことになります。 ・呼吸力を使って腕を頭上まで上げる動作を,合気会では言いませんが便利なので「合気上げ」とここでは使います。 ・腕を持つ受けが,体を固めてしまうと手が外れてしまいます。それほど強い動きです。 ・受けとしては、手が外れると直ちに取りから当身が来ますので、手を持ち続けれるように努力します。 ・投げです。重力落としで投げます。 相手の上に自分の体重を一瞬載せます。 あとは地球が受けを引っ張っていきます。 (^-^)v |
[▲Top]

技に込められた極意
わざにひめられたごくい
| 固め技 | 講習内容 |
| イントロ | <技の中の極意> ・武田惣角先生は,皆に見せる,演武のときと教えるときの技は異なったといわれています。 その理由は,受身を満足にできないひとに合気柔術を行えば, けが人が続出してしまうからと思っています。 そのため,関節技やツボ攻めで,痛いことで相手を動かす技を まず教え,技が習得するにしたがって,合気動作を使った技に 移行するとの方法をとったと考えています。 ・固め技,一教から四教の中で,この「痛い」技は,二教~四教です。 一教は,二教~四教に比べ「痛く」はありません。 ただ,大東流では,肘を逆関節に取ったので,痛い技だったのかもしれません。 ・一番最初に教える固め技である一教は,極意がたくさん詰まっています。 ここでは,それを見ていきたいと思います。 極意を理解するには,一教をある程度,柔術技として修得しておく必要があります。 (^-^)v |
| 固め技 | 講習内容 |
| 一教 | <一教に隠された極意> ここでは,正面打ち一教で,一教に秘められた極意を見ていきたく思います。 <打ちに対する極意> <返しに対する極意> <落としに対する極意> 具体的な一教の合気三原則を使った説明は,合気道講習2「一教」を参照ください。 (^-^)v |
| 投げ技 | 講習内容 |
| 入身投げ | <入身投げに隠された極意> ★★★★ 入身投げには,全ての動作で,極意動作,合気動作がつまっています。 正面打ち入身投げの合気動作のポイントは以下です。 ・合気捌き: (一教運動合気上げ捌き,軽い「削ぎ出し」) ・真中へ入身:相手の側面裏へ ・重力落とし:相手の上腕から内肘にかけて。 削ぎ落し続けた重力落とし。 ・合気上げ起こし:体は垂直に膝を緩めて,指先から天井に向け合気上げ。 起しと体の合気で行うその場投げでは,入身投げとして技は終了。 ・真中維持で伸張力による投げ:親指下で指先から床に向かって突き出し投げます。 具体的な入身投げの合気三原則を使った説明は,合気道講習2「入身投げ」を参照ください。 (^-^)v |
[▲Top]

では,「合気道の極意を技に展開して」と題する講習のシリーズの第三回として行った「基本の技法に深く蔵されている極意」についての講習を終えたいと思います。 普段稽古している技の中に,「極意」を見出すことができると,同じ技で,身長が190cm,体重が100kg超の相手にも対応することができるようになります。 本日の講習のテキストや市販されている本はありませんが, 技法としての合気については,武田惣角先生の直弟子の佐川幸義先生に関する 「孤塁の名人」「透明な力」が参考になります。ここ本にでてくる動きをすべて体現するように考えてみてください。ともに文庫本で購入できましたが現在では絶版になってしまいました。「孤塁の名人」の方は,電子書籍で購入可能です。 合気の動きについては,岡本正剛先生のビデオや菅沼守人先生の講習会の様子がyoutubeで見ることができます。探してみてください。 合気は自分で考えない限り自分のものになりません。自分に対する「マインドコントロール」を上手くつかって獲得してください。頑張ってください。 参加,ありがとうございました。 (^-^)v |

[▲Top]

本ホームページの作成者・管理者: 高橋達人 たかはしたつひと tatsuaiki7@gmail.com
